About当店について

魚河岸と共に歩み、おかげさまで150年。
令和四年 神楽月吉日



沿革
1872年(明治5年)〜
- 1872年(明治5年)
「源正久」は、明治5年に大阪での代々の刀鍛冶より出刃鍛冶に転じる。
同時に「源正久」の次男中村鉄次郎が東京において打刃物業を開業、初代「東源正久(あずまみなもとのまさひさ)」を名乗る。
店舗を当時の魚河岸の所在地である日本橋の本町に、工場(「正久刃物製作所」)を神田紺屋町に構える。- 明治40年代初頭
海外から洋式刃物製造技術を導入。
技師 隅田太郎をヨーロッパおよびアメリカへ派遣し、洋式刃物製造技術を取得・移入。
それまでの和式料理刃物部門に加えて、洋式技術による機械刃物部門(現「正久エンジニアリング」)を併設。この技法が関東における「牛刀」の発祥となる。
なお、この技術を習得した職人たちの多くはいわゆる「牛刀」製作により独立し、日本における牛刀の急速な普及に大きく貢献。
また、鮪庖丁においては胴割りをせずに体長を確保できる製法を確立し、現在の卸庖丁(大庖丁・長庖丁)が完成。
1912年(大正1年)〜
- 1912年(大正1年)
大蔵省造幣局御用達 二代目始業 工場移転。
独自の機械刃物製造技術を駆使した紙幣断裁機を大蔵省造幣局に納品。- 1918年(大正7年)
小川五郎左衛門(明治36年生—昭和45年没)始業。
後継者となり二代目「東源正久」を名乗る。- 1923年(大正12年)
関東大震災により店舗・工場とも焼失。
店舗は以前同様、日本橋本町に再建し、工場は高田馬場に移転。
1930年(昭和5年)〜
- 1930年(昭和5年)
日本橋より築地へ魚河岸移転 築地本店開設。
魚河岸の築地移転にともない築地店を開設、以後築地を本店とする。
機械刃物部門が大型のマグロ庖丁製造を一手に担うと同時に、卸売市場荷受・大物業界(鮪商等)の店舗の大半に専門解体庖丁を納品。
また、太平洋戦争中には陸軍の指定を受けて「昭和新刀」も作成・納品。- 1944年(昭和19年)
工場再移転。
戦災により高田馬場の工場焼失、要町を経て下落合に移転。- 1952年(昭和27年)
三代目始業 修行。
二代目小川五郎左衛門 長男小川三夫(昭和8年生—平成23年没)始業。
刀鍛冶の流れを守る打刃物業として、代々の方針により二代目と二代目兄弟弟子の許で「鍛冶と研ぎ」双方の修行を併せて行い、後継者として薫陶を受ける。- 1964年(昭和39年)
三代目襲名。
三代目の結婚により、それまで日本橋店に単身居住していた三代目が築地の本店に、本店に居住していた二代目が日本橋店に住居を移す。
これより小川三夫が正式に三代目「東源正久」を名乗ることとなる。
2001年(平成21年)〜
- 2009年(平成21年)
五代目始業 修行。
三代目門弟 石川裕基始業。
三代目の許で修行を始めると同時に、東源正久の孫弟子に当たる製造現場等で製造工程からの指導を受け研鑽を積む。- 2011年(平成23年)
四代目継承。
三代目、長女小川由香を四代目に、門弟 石川裕基を後継者に指名し身罷る。- 2016年(平成28年)
株式会社改組。
東京都卸売市場移転に伴う関連業者参画のため、東源正久改め株式会社 東源正久商店に改組。
代表取締役に小川由香、専務取締役に石川裕基が就任する。- 2018年(平成30年)
豊洲市場 開場。
東京都中央卸売市場 築地商業協同組合(現 豊洲市場商業協同組合)に参入。
東京都中央卸売市場の豊洲移転に伴い、豊洲市場 水産仲卸売場棟4階「魚がし横丁」内に豊洲市場店を開設。
これより石川裕基が正式に五代目「東源正久」を名乗ることとなる。- 2022年(令和4年)
包丁鍛冶として創業150周年を迎える。
当年150周年を迎えることができましたのも偏に永きに亘るお客様のご愛顧の賜物と感謝申し上げます。
今後とも変わらぬご厚誼のほど伏してお願い申し上げます。
本店

| 住所 | 〒104-0045 東京都中央区築地4-13-7 [Google マップを見る] |
|---|---|
| TEL/FAX | 03-3541-8619 |
| 営業時間 | 5:30〜15:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日・市場休市日(一部を除く) ※詳しくは営業日カレンダーをご参照下さい |
電車でお越しのお客様へ
- 日比谷線 「築地」駅より徒歩5分
- 有楽町線 「新富町」駅より徒歩約10分
- 大江戸線 「築地市場」駅より徒歩約5分
バスでお越しのお客様へ
- バス停 「築地三丁目」より徒歩約5分
- バス停 「築地六丁目」より徒歩約3分

豊洲市場店
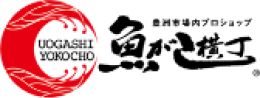
| 住所 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目5番1号6街区水産仲卸売場棟4階68 [Google マップを見る] |
|---|---|
| TEL | 03-6633-0878 |
| 営業時間 | 5:00〜12:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日・市場休市日(一部を除く) ※詳しくは営業日カレンダーをご参照下さい |
電車でお越しのお客様へ
- ゆりかもめ 「市場前駅」より徒歩約15分
バスでお越しのお客様へ
- バス停 「水産仲卸棟」より徒歩約15分
- バス停 「豊洲市場」より徒歩約20分

営業日カレンダー
ご来店の際は営業日をご確認の上お越しいただきますよう、よろしくお願いいたします。
【本店】 5:30〜15:00
【豊洲市場店】5:00〜12:00
■休業日■本店のみ営業(9:00~14:00)、豊洲市場店休業


